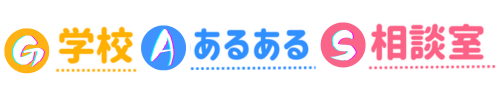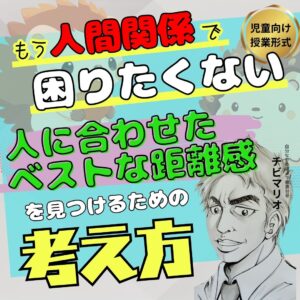【トラブル対応の基本】問題を成長につなげるために教師がやるべきこと

子どものトラブルって、本当に面倒ですよね?

大きないじめとか暴力とかですか?

いえ、そこまで大きなことではないのですが、
ポコポコ起こる子どもたちの問題が…

それは適切に対応することで、
むしろプラスに変えるきっかけなんですよ!
「先生、〇〇さんと△△ちゃんがケンカしてる~!」
「先生、☆☆さんが泣いてます!」
「先生…私~~ということで悩んでいます……」
子どもたちと過ごす毎日の中で
こういうトラブルの報告系で
話しかけられることってないですか?
そのたびに
先生の心の中に
「ふぅぅぅ~……」というため息が
生まれていませんか?
でも、実は逆です!
こういう子どもたちからの投げかけは
むしろ
成長するきっかけに使えます!
「ラッキー」なんです!
もちろん
そんな日々が毎日毎日続くと
そりゃ先生の気持ちも
しんどいな…
ってなるのも重々分かります
でも、そんなときこそ
問題を客観的にとらえるんです
「自分の問題」ではなく
「その子の問題」「クラスの問題」と
とらえることが大事なんです
子どもなんて問題を起こして当然!
という気持ちで
トラブルと向き合い
基本に忠実な対応をすることで
子どもたちが起こす
トラブルの数は
圧倒的に減ってくるはずです
今回は特殊なケースを除き
極々一般的なトラブルに対する
「基本的な対応」を
いっしょに考えていきましょう!
トラブル対応の超超超キーポイントは
「トラブルをきっかけに成長した点を見つけて伝える」 です。
①トラブルのとらえ方
(1)問題発生は担任の責任ではない
子どもたちが問題を起こした
そうなった瞬間
担任として
「自分の責任だ…」と
感じてしまっていませんか?
全然違います!!
ほとんどの問題は
子どもたち自身にあります
また子どもたち自身も
悪いのではなく
そのトラブルという事象自体が
良くないんだという感覚です
もちろん
だからと言って
「先生は何もしない」のではなく
そんな子どもたちのために
何ができるのかを
考える必要があります
ただ
自分の責任だ…
と凹む必要は全くないということを
まずは忘れないでください
とは言いながらも
保護者や管理職の中には
問題が起こるたびに
「担任の責任」という空気を
あからさまに出してくる人も
多く存在します
まぁ
その対応は複雑なので
今回は省略し
一言で表すと……
「無視」です!!
(2)問題はクラスを変えるための教材
その「問題の責任は自分ではない」と
割り切った上で
次に大事な感覚が
「これを機に子どもを…
クラスを変えていこう!」
です。
道徳の教科書に載っている教材以上に
より身近な教材が
自分たちの身の回りで起こる
トラブルです
問題を「悪」とするのではなく
「いい教材が見つかった」と
考えることが
子どもたちを成長させる
きっかけにつなぐ方法です
(3)問題が2学期以降に減っていけばOK
1学期のトラブルは当然だし
むしろ喜んで問題を発見してもいいと
私は思っています
そのたびに
子どもたちは成長していけるので
1学期に
ドンドン成長する方が有難いからです
で、
2学期…、3学期…と
進むにつれて
数が減っていけば
「あのときのトラブル」が
「いい経験」と
呼べるようになるんです
②トラブル対応の流れ
それでは具体的に
トラブルが発生した場合
どのような手順で対応すれば
いいのでしょうか?
(1)焦らないで対応する
「先生~!!〇〇ちゃんが……」
こういう報告を聞いたとき
若手の先生や
自分の責任と捉える先生は
ちょいと焦ってしまいがちです
「どうした!?」と
バタバタしたり…
「何があった!?」と
少し強めの口調になったり…
でも、
そういう態度を出してしまうと
報告に来た子や
まわりにいる子は
「トラブルが起こった=良くない=怒られる」
という構図が
頭の中に定着してしまいます
先ほども言ったように
「トラブル=悪」ではないので
冷静に
「落ち着いて事情を話してね」
と対応することが第一です!
(2)当事者から情報を聞き取る
1人の問題ならもちろん
2人以上であっても
基本的には1人ずつ順番に
事情や気持ちを
聞いていきます
※1対1の問題に限り、時短のために同時で聞くこともあり
ここではとにかく
事実(子どもの素直な表現)を
そのまま聞き出すことが
とても重要です
「うんうん、それで?」
「なるほど。で、どうなった?」
など、
自分の先入観は一切入れず
子どもの心を引き出すんです
ここで
「悪口を言われたの?」
などの質問を入れることで
本当はそうでないのに
そのような気持ちになってしまい
間違った情報を伝えてしまう子も
いるからです
1人目と2人目で
情報が違っていたとしても
ここでは
素直に聞き出すことに
専念してください
(3)周りの子から情報を聞き取る
どの子から聞いても
同じ情報で
ほとんどズレがない場合は
この段階を省略できます
ただ、
ほとんどの場合
何らかの場面で
子どもたちの意見が食い違っています
そんな場合、
この段階で(2)の情報の信ぴょう性を
確かめます
かたよった仲間からでなく
平等に判断できそうな
第三者から
聞き出すことが大切です
どちらかに
肩入れするような子に
ここの情報を聞き取ってしまうと
どちらか一方の
不信感につながるので
この段階は
慎重に取り組む必要がありますね
(4)ここまで集めた情報を客観的に整理・分析する【重要】
ここが意外と重要です!!
子どもたちから聞き取った情報を
何も考えずに
そのまま持ち出して
当事者を鉢合わせるのは
絶対にキケンです
トラブルの深さが
余計に増してしまう可能性だって
考えられます!
この段階で
多方から集まった情報を
きちんと整理し
どう分析していくのかが
本当に大事です
どのように指導することが
子どもたちに効果的か…
見通しをもった上で
当事者の顔合わせが重要です!
場合によっては
もう一度
どちらかから情報を聞き取ることが
必要なこともあります
また、
当事者同士を
いっしょにした話し合いを
しなくてもいい…
もしくは
しない方がいい場合も
考えられます
一概に
「情報を聞く」
「すり合わせる」
「謝罪する」という
超シンプルなトラブル対応にせず
この「分析する」という段階を
ぜひ
忘れないでください
(5)対応する先生を「1人」か「チーム」か判断する
その(4)の分析で
「どのように指導していくか」
に合わせて
「だれが対応するか」
も考える必要があります
もうすべてを担任一人が背負う時代は
終わっています!
学年、学校という
チームで
問題に対応することが
求められる時代です
「だれが」という役割を分担したり
「いつ」「どこで」などのタイミングを考えたり
「どのように」指導するのかが
人によって変わらないように
チームで考えを共有したりすることが
とてもとても重要です!
生活指導担当や
管理職が
そのコーディネートの役割を
担える学校はステキですね
(6)該当者全員を同じ場に集め、話し合わせる
そこまで入念に考えた上で
やっと
当事者同士を
同じ場所に集めて
お互いの気持ちや事情を伝え合います
分析や役割分担の効果を
ここで発揮させて
話し合いをうまく
コーディネートしていくんです
ここが
うまくいくかいかないかで
子どもたちは
「本気で反省」
するかしないかが決まります
だからこそ(4)や(5)が重要なんです!
そして
少しでも反省が必要な子は
必ず
この当事者たちがいる前で
「ごめんなさい」を
言える環境を作りましょう
「謝る」という行為が
あるのかないのかで
今後もモヤモヤにも関わってくるし
「反省できる子」にするためにも
この謝罪の時間は
大事にしたいですね!
(7)事後の報告 <事実>
そして
これは社会人として
当然の流れ
「報告」ですね
ここまでの段階で
生活指導や他の先生が
関わっている場合もありますが
ひと段落した時点で
必ず
管理職には
何があったのか
どう対応したのか
を報告するようにしましょう!
こういう報告を
快く聞き入れてくれる管理職は
本当に最高です
そんな職場は幸せです
だいたいはそうですが、
たまにいます!
そういう報告を
嫌そうに聞く管理職!
もっと言うなら
その報告を聞いて
怒ったり注意したりしてくる管理職!
まぁ……
「無視」しましょう(笑)
そして、もちろん
その日のうちに
該当児童の保護者には
必ず連絡するようにしましょう!
あったことの事実はもちろん
そのあとの反省タイムでも
子どもの様子も伝えてください
学校での反省が見られるようなら
保護者から子どもへの指導は
「知っておくだけで何もしなくてもいい」
と伝えることもあっていいと思います
2回も叱られると
子どもの心も折れちゃいますからね
もちろん
場合によっては
家でも指導をお願いすることも必要です
そして
先生や家庭の事情によって
その日のうちに
連絡できなかったとしても
必ず携帯電話に
着信履歴は
入れるようにしましょう!
トラブルの報告は
決して気持ちのいいものではありませんが
ここの連絡を
スルーしてしまうと
のちのち
違う問題に
発展してしまう可能性もあるからです
(8)事後の報告 <成長点>
で!!!
ここが
トラブル対応の「基本」で
私が最も重要なポイント
と思うところです
多くの先生は
この(8)をすることなく
問題解決としてしまいます。
ただ、
この(8)を入れることで
今後の子どもの様子が
各段に変わります!
同じ問題を起こす可能性が
圧倒的に減ります!
それが
「先日のトラブルをきっかけに成長したことを伝える」
です。
保護者の立場からして
前回のトラブル報告だけだと
少なからず
心配要素が残ってしまいます
だからこそ
このトラブルをきっかけに成長した点を
1、2週間後に
報告してあげることで
保護者からはもちろん
子どもからの信頼が
爆上がりするんです!!
「前回はイラっとしてすぐに手を出してしまいましたが
今回はグッとこらえていましたよ」
「前回は人の悪口を言っていたけど
今回は、そんな友だちに注意していましたよ」
などです。
子どもの気持ちとして
「前回のトラブルで先生に嫌われたかも…」
「前回いらんことしてしまった…」
のようなネガティブな感情を持ちます
それを一掃する方法が
この
「トラブルからの成長」を見つけて
ほめてあげることです!
保護者に連絡することで
家で褒めてもらえます
そうすることで
子どもは
「先生がわざわざ僕の成長を報告してくれた」
というハッピーな気持ちになれます
これがあるかないかで
子どもの今後が変わるんです!!
③トラブル発生時にやってはいけないこと
子どもへの指導は
早いに越したことはありません
でも
その焦りから
やってしまいがちなミスが
授業時間に
みんなの前で
事情を聞き出したり
反省会を始めたり
することです
これは絶対にダメです!!
シンプルに思うでしょ!?
「いや…おれら関係ないやん!!」って!
また
みんなの前で指導しないにしても
他の子どもたちを放置して
別室で対応するのも良くありません
そういう時間にこそ
子どもたちの気がゆるみ
また違うトラブルが
発生してしまう危険性があるからです
冷静に考えたら
誰でも分かる感覚ですが
トラブルを焦って捉えてしまう先生は
よくやってしまうミスです
そういう誤った対応は
該当者も反省しにくいし
他の子からの先生への信頼を
大きく失うことになりかねません
焦らず考え、
次の休み時間や放課後などの
他の子に影響の出ない時間に
トラブル対応をすることを
忘れないようにしましょう!!
PS:
ただ、
「チャイム着席を守ろう」とか
「言葉遣いに気を付けよう」などの
全体にかかわるような指導を
特定の子に話すスタイルで
クラス全体に共有するのは
意図的にするのなら
もちろん大アリです!!
④まとめ
確かに
「トラブルはしんどい」
でも
「トラブルは子どもを成長させる」
この感覚を忘れず
そして
「トラブル対応の基本」を
落ち着いて対応できれば
間違いなく
子どもたちは変わります
また
トラブルが発生したことをきっかけに
保護者からの信頼にもつながります
トラブル対応の超超超キーポイントは
「トラブルをきっかけに成長した点を見つける・伝える」
です。
ぜひ
子どもたちのトラブルを
前向きにとらえ
成長できるきっかけに
変えていってください!