【教師必見】保護者から信頼される教師が必ず意識している心構え ベスト3

保護者からの苦情や連絡が
とまらない…

それは「保護者からの信頼」が
足りていないのかもしれませんね。

いやいや、子どもからの信頼は分かるけど、
保護者からの信頼って必要なの?

保護者に信頼されると、
子どもや学級が変わるんですよ!
教師の悩みの種の大きな1つ。それが「保護者からのクレーム」です。
クレーム対応に追われると、心も体も疲れ果て、本来大事にすべき「子どものための時間」が使えなくなりますよね。
ただ、あることを意識すると、クレームの数は圧倒的に減ります。
それはやっぱり……「信頼を得ること」です。
保護者もやはり「どんな不満なのか」よりも「誰に対する不満なのか」でモヤモヤしてしまいがちです。
以下の3つの心構えを参考にしてもらえれば、修了式の日、保護者たちから「〇〇先生、来年もうちの子を担任してくださいね。よろしく!」と言ってもらえる教師になれるはずです。
「保護者からの信頼」って必要なの?
もちろん「子どもからの信頼」が一番です。
でも保護者と子どもは密接につながっています。
確かに保護者によって
学校に…もしくは担任に
求めているものは違ってきます。
でも、保護者の意見の根底には
すべて「子どものため」という想いがあります。
(一部の過剰なクレームを除く)
「子どものために一生懸命な先生」
という信頼を得ることができたなら、
少々のミスをしてしまっても
ちょっとした不満があっても
「あの先生なら…」と許容してもらえます。
むしろサポートしてくれます。
逆に
「信頼できない先生」と思われてしまうと…
ちょっとしたミスでも不満につながります。
学級トラブルのすべてが担任のせいにされます。
9割の「頑張り」より1割の「ゆとり」に目をつけられます。
一生懸命な部分は見てもらえず
足りない点ばかり指摘されると
そりゃしんどくなっちゃいますよね。
では、「保護者から信頼される先生」とは
具体的にどういう人でしょうか?
それは
「情報を伝えてくれる」
「子どものことを大事にしてくれる」
「考えていることが明確である」
だと思います。
それぞれに必要な行動を詳しく見ていきましょう。
心構え①「こまめな連絡で、保護者に情報を伝える」
保護者にとって
「学校からの電話(連絡)」と言えば
「トラブルを起こした」
「ケガをした」
「熱を出した」などの
ネガティブ情報が大半だと感じます。
特に今まで、
よくトラブルに関わっていた
子どもの保護者はなおさらです。
「学校から電話」が
かかってくるたびに憂鬱になります。
だから、それを逆手に取るんです。
「学校からの電話」で
ちょっとハッピーになってもらうんです。
学級がスタートする4月の間に
できるだけ早く
全部の家庭に
子どもの頑張っている様子を
電話で伝えるんです。
「朝、元気なあいさつをしてくれます」
「手を挙げて発表してくれました」
「先生のお手伝いをしてくれます」
「いつも元気に外で遊んでいます」
などなど。
どんな小さなことでも構わないので
その「頑張っていること『のみ』」を
伝える電話をするんです。
超大事なポイントは
「プラス情報『のみ』」
という点。
そこが保護者にとっては
「わざわざそんなことだけで連絡くれるなんて…」
「今年の先生は安心して預けられる…」
って思ってもらえるポイントにつながります。
保護者との最初の会話が
「こういうプラス情報のみ」になると
今後、トラブルなどの連絡の際も
快く聞き入れてもらえます。
もちろん、
そうは言っても4月の早い段階で
ケガやトラブルの連絡が
必要になる場面もあるでしょう。
でも、そんなときでも、
いや…そんなときこそ、
ちょっとしたハッピー情報も
合わせて伝えることを
心がけるだけで
今後の保護者との関係も
子どもとの関係も
良好に進められると思います。
ただ、
今回の「速攻プラス情報 電話作戦」を
実行するためには
やっぱり先生の気持ちのベースに
「子どものことを大事にしたい」
「子どものことが好き」は
必要ですけどね。
うわべだけの作戦じゃ無理でしょう。
心構え②「子どもと同じ目線で接する場面を作る」
子どもたちに指示を出したり
集団としてまとめたりすることは
教師として不可欠です。
リーダーとして
引っ張る姿勢を見せることが重要です。
ただ何でもかんでも上から目線での
指示や発言になると
子どもは命令されていると感じ
反抗的な態度を
取りがちになります。
大事にされていると感じてもらうためにも
同じ目線での行動や発言が
必要になってくるのです。
具体的には…
①「一緒に遊ぶ」!!
授業の一環としてではなく
ちょっとした休み時間の交流で
子どもの本音が見られます。
また、子どもも先生のことを
同じ目線で見て
ざっくばらんに関わりやすい空気になります。
トランプのような教室遊び…
ドッヂボールのような外遊び…
たった5分でも
「先生と遊んだ」という時間が
子どもからの信頼につながります。
そして家に帰ってから
子どもが親に伝える
「今日先生と遊んだんだよ」という一言が
保護者からの大きな信頼につながります。
また
②「悩み相談」に対して
真摯に向き合う姿勢も
めちゃくちゃ効果的です。
「先生が悩みを聞いてくれた」
「もうその悩みは先生に伝えたよ」
という子どもの一言で
保護者からの信頼度は急上昇です。
ただ、
子どもは、みんながみんな
「せんせ~い」と
悩みを打ち明けてくれるもんではありません。
そこで有効的な方法が
「日記」のような作文です。
何気ない日常のことであっても
そこからうかがえる
不安や悩み…に限らず
ワクワク、ドキドキな気持ち…でも
なんでもOK!
子どもの気持ちに対して
先生の真摯な態度を
文字でも対面でも
表現することが
子どもにとって
「大事にされている」
「同じ目線で接してくれている」
と感じるきっかけになります。
そして「遊び」と同様
それが回り回って
保護者からの信頼へとつながるんです。
心構え③「学校や学級の方針を明確にする」
保護者が学校やクラス、担任に対して
不信感を抱く原因の1つに
「不透明感」や「軸のなさ」が
考えられます。
「学校は何をやっているんだろう?」
「前言っていたことと違うんじゃない?」
そんな感情が積もりに積もると
大した問題でなくても
めちゃくちゃ大きな問題として
保護者はとらえてしまいます。
そうならないためにも
始業式の日に…
新学期1週目以内に…
1回目の懇談会で…
とにかく
早い段階で、
明確かつ軸の通った「経営方針」を
保護者に…
もちろん子どもに…
伝えることが大事です!
その「経営方針」は
「どういう力をつけてほしい」
「どういう学級を目指したい」
「どういう場面では厳しく指導する」など
自分が大事にしたいことを
ハッキリさせることが目的です。
なので、
毎年毎年大きく変わることはなく
一度、真剣に決めてしまえば
あとはその学級に合わせて
微調整をしていくだけで十分です。
経営方針のくわしい立て方は
また別でお伝えできればと思います。 <後日リンク>
大事なことは
「経営方針を決めること」以上に
「その方針を公開すること」
「方針を忠実に守ること」
なんです!
そして、その方針に従って
1年間の学級経営を行えば、
保護者からの不必要なクレームは減るはずです。
少なくとも
理不尽なクレームに
振り回されることはなくなります。
また
自分の「経営方針」に沿った
日々の活動や様子を
学級通信にのせて伝えれば
保護者からの信頼は
ドンドンドンドン強いものに
なっていくはずです。
学級通信についても、
また別でお伝えしたいと思います。 《後日リンク》
軸をブラさない態度は
間違いなく効果的です。
(※注意 共感が得られない軸は逆効果)
一貫した想いで
子どもと接し続けることが
子どもからの
また、保護者からの
大きな信頼につながります。
まとめ
保護者は決して「敵」ではありません。
学級経営に欠かせない大切な「味方」です。
もちろん、子どもが一番なので
「保護者のための行動」にはならないよう
気をつける必要があります。
ただ、子どもとはもちろん、
保護者とうまくつながれば、
学級経営がもっと円滑に進むし、
教師としての楽しさが2倍、3倍に膨らみます。
ぜひ、上記3つの心構えを意識して
「〇〇先生、来年もうちの子よろしくね!」
と言ってもらえるよう
先手必勝を心がけてみませんか?
本当に快感ですよ(^^)
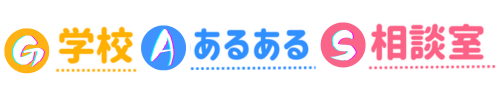
-1-300x300.png)
-300x300.png)