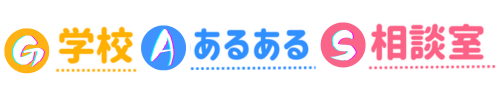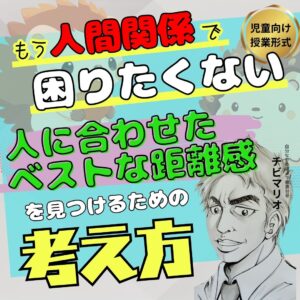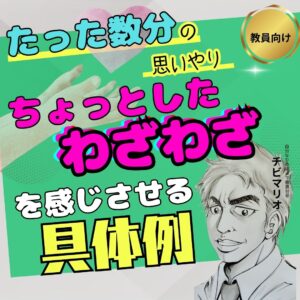【落ち着いたクラスに】クツをそろえる習慣がクラスを変える

いつもガチャガチャしているんです、うちのクラス…

数人が常に落ち着かないというタイプですか?

いえ、特定の子というより…全体的な雰囲気が…

そういうパターンに効果的な方法は、
ズバリ…くつそろえ!!
クラスがガチャガチャしている…
何となく静かにはなるけど…
全体的に指示があんまり入らない気が…
そんな悩みは授業をする上で
誰しもが感じるモヤモヤではないでしょうか?
もちろん
個別に対応が必要なケースも多く存在しますが
全体的な落ち着きを必要とする場合に
効果的な方法があるんです
それが
「クツ箱のクツをそろえる」です
クツ箱のクツをそろえることは
最終目的ではなく
その過程を通して子どもたちが
「心が落ち着く」
「細かいところに気が利く」
「やればできるという自信が生まれる」
などのメリットがあります!
どうやって
クツをそろえるような子どもたちに…
クラスになっていくのか
順を追って
考えていきましょう!
①クツそろえが重要な理由
身の回りを整理する上で
いろんな物があると思いますが
その中でもあえて
「クツ」にしているのには
理由があるんです
それが以下の3つです!
(1)やろうと思えば誰でもできる
「算数で100点」とか
「なわとびを10回」とか
「元気なあいさつ」のような取り組みだと
個性や状況によっては
ハードルが高いと感じる子もいます
それに比べて
この「クツをそろえる」は
「やろう」と思えば
必ずだれでもできるんです
もちろん特性によっては
クツをそろえることが難しいと
感じる子もいますが
まわりの子がサポートすれば
クリアできちゃうんです
(2)控えめな性格な子でも活躍できる
この「クツそろえ」は
前回紹介した「あいさつ」とは違い
静かな性格の子でも
気軽に取り組みやすい活動です
むしろ
そういう落ち着いた性格の子ほど
いろんなところに気が利き
活躍できる場面になりやすいんです
そして
どうしてもクツをそろえられない子がいても
そういう仲間の協力で
助け合うことができるのも
また「クツそろえ」の魅力の1つですね
(3)できていることを実感しやすい
クツ箱を見ると
間違いなく
「できた」「できていない」が
わかります!
だから
子どもたち自身で
自分たちの成長を
実感したり
反省したりできるんです
「できたかできていないか」という
明確な指標があるのは
子どもたちにとって
大きな大きなメリットなんです
②クツそろえができるまでの流れ
では、そんな「クツそろえ」を
みんなが意識して
みんなで整ったクツ箱を
作っていくまでに
どんな流れが必要なのか
考えていきましょう!
(1)クツがそろっている子のクツ箱の写真を撮る
必ず一人は美しくクツをそろえている子がいます
そのクツ箱の写真をとって
みんなでシェアします
みんなにどう思うかたずねて
「クツがそろっていて気持ちいい」
などの感想が出るとラッキー!
(2)みんなに投げかけて人数を増やす
「じゃあ明日はみんなもやってみよう」と
投げかけます
そうすると必ず
数人のクツがそろっているはずです!
これもまた
写真におさめて
増えたことを実感させたいですね
(3)クツをそろえることの気持ちよさを感じてもらう
3個、4個連続して
クツがそろっているクツ箱の
写真を撮って、みんなで見てみます
すると
「うぉぉ~」などの
感嘆が聞こえてくるはず
「どう?」
と投げかけると
「なんか気持ちいい!」
「いつか1列そろってビンゴになるんじゃない?」
など
楽しみ出している発言も
生まれてくるかもしれません。
(4)「かかとをそろえる」というクツのそろえ方も統一する
このあたりで
ただ「クツをそろえる」といっても
そろっているだけではなく
より美しいクツの置き方について
みんなで考えます
クツ箱の奥でそろっているパターンと
クツ箱の手前でそろっているパターン
両方の写真を見比べて
どう思うのか
みんなに聞いてみます
たぶん
かかとがそろっている方が
みんなのクツのサイズに関係なく
美しく整っている
と子どもたちは感じると思います
そうしたら
今後は
「かかとをそろえよう」
という意識が芽生えて
より一層
クツ箱への意識が高まります
(5)状況によっては、コッソリ先生がそろえて写真を撮る
この流れで半数近くのクツ箱は
そろい始めます!
でも、一定数は
いつまで経っても
美しくそろうことはないかもしれません
そんなときは
コッソリ先生がそろえてあげます
これができるのが
「クツ」であるメリットです
みんなの目線がないところで
サポートできるからです
明らかに
変な置き方を除いて
ほんの少しずれているだけのクツを
先生がこっそりそろえて
写真におさめます
自分では気づいていなくても
きちんとそろえられている
ということを
みんなの前でほめられると
明日から
ほんの少し意識する子が増えてくるはずです
(6)コッソリ作戦がおかしいと感じる子がいたら
ただ、
「え、俺、今日の朝、クツそろえてないで!」
と気づく子もいます
そういうときはこう伝えます
「みんなのために、クツを整えている子がいるんだね」
と。
「いつまでも人に甘えているのは良くないけれど
そうやって人のために動ける子が
クラスにいてくれるって本当にステキだね…」
と投げかけると
次の日からは
友だち同士でそろえ合いが
始まります。
あとは本当に全員のクツがそろうのを待ちます
(7)全員ができたときには、みんなで喜ぶ
そして
いつの日か
待ち続けることで
全員のクツがそろう日がきます!
その瞬間の写真をおさめ
みんなでシェアしたり
学級通信にのせたりすることで
子どもたちの中で
「やったぁ!」
「気持ちいい!」
という感情が生まれてくるんです。
③クツをそろえることのメリット
そんな「クツそろえ」を
みんなが意識して
みんなで達成できるようになると
いろんなメリットが生まれます
(1)心が落ち着く
クツをそろえずに置いてしまう子は
何も考えずに
クツを脱いでクツを置きます
でも
クツをそろえる意識が芽生え始めると
まずはクツ箱の前で
いったん
落ち着く必要が生まれます
「かかとをそろえよう」という
この一瞬の落ち着きが
実は
めちゃくちゃ大事なんです!
その落ち着きをもって
1日が始まる教室に入ることで
あいさつも変わるし
行動も変わるんです
(2)教室内の物も整い始める
クツがそろう気持ち良さを
感じられるようになると
「他の物もそろえたい」という気持ちが
芽生え始める子が必ず現れます!
よくあるパターンは
・ランドセル
・つくえ
・教室保管の教科書
・机の中
などです。
そういう教室内の環境が整い始めると
ようやくここで
子どもたちの教室での行動が
落ち着き始め
子どもたちも心の落ち着きを
感じられるようになります
(3)やればできるという自信が生まれる
まちがいなく
「できた」
「みんなでできた」
ということが明確にわかるため
子どもたちの中で
「おれたちならできる!」
「なんかこのクラスいい感じ!」と
感じることができます
そうなると
「クツそろえ」をきっかけに
いろんな活動や行事でも
自信を持って取り組むようになります!
そして
他学年と関わるときや
校外に出て活動するとき
持ち物をキッチリそろえる子どもたちを見て
他の人たちにも
ほめてもらうことができます!
それがまた
子どもたちの自信につながるんです!
「物を整えて置く」というのは
どんな人にとっても
「できている状態」が分かりやすいので
本当にいろんな人から
ほめてもらうきっかけになるんです!
④クツをそろえるクラスにする上での注意点
ただ、
ここでも注意すべきことがあります
それは
「無理やりさせない」
ということです
・自然とやっている人をほめる
・そんな流れに乗る人が増える
ここまでは絶対に
うまくいきます!
ただ、問題はここからで
そんな流れに乗らない子も絶対にいます!
また
やろうとは思っても
持続できない子も
絶対にいます!!
ここで
「くつをそろえていない子がいます!」
という先生からの指摘や
「ちゃんとやれよ!」
というクラスメイトからの指摘は
達成したときの
真の喜びにつながらなくなる
原因となってしまいます。
じゃあどうすればいいのか…
先ほどの
「先生コッソリ作戦」
か
「優しい子どもの行動」
を待つんです。
また
クツ箱の前で
先生が待機していて
あいさつをしているフリをして
コッソリ
「おっし~、あと少し」
「あ~ちょっとズレてんな~」など
その場で
ほんの少し声かけをしてみます
その声かけだけで
素直に整える子もいるでしょう
とにかく
叱るのはもちろん
「やらせよう」とするのではなく
気長に待ち続ける
いつか
全員のクツがそろった初日
「みんなのクツがそろいました!」
とみんなに投げかけて
実際の写真を見ることで
自分たちの成長を実感できます
⑤まとめ
意外なようで理にかなった
「クラスを落ち着かせる方法」
それが
「クツそろえ」です。
「できた」を実感できる
そして
教室内じゃないからこそ
実感させやすい方法
それが
「クツそろえ」です。
「クツをそろえよう」という
1つの同じ意識に向かって
クラスのみんなが取り組むことで
クラスが変わる!
そんなに難しいことではないからこそ
一度、
実際に試してみてください
効果を感じられると
先生も子どもも
もっともっと楽しくなってくるはずです!