【教師必見】子どもから信頼される教師が必ず意識している心構え ベスト3

子どもたちが全く私の指示を聞いてくれません。
どうしたらいいんだろう??

それはズバリ
「子どもとの信頼関係」の問題だろうね。

でもそんなに
簡単に信頼って築けないよね?

確かにそうだね。
でも、めっちゃ大事な心構えは押さえておく必要があると思うよ。
「子どもが指示を聞いてくれない」
「授業がうまくいかない」
「クラスが崩壊しそう」
この解決方法の根底に必要なこと……それはズバリ「信頼を得る」です。
子どもは「どんな指示なのか」よりも「だれからの指示なのか」を重要視しがちです。つまり、「人」で選択しているのです。悲しいかな、これが現実です。
以下の3つの心構えを参考にしてもらえれば、学年が終わる修了式の日、子どもたちから「担任が〇〇先生で本当によかった。ありがとう!」と言ってもらえる教師に、きっとなれるはずです!
そもそも信頼される必要ってあるの?
大ありです!
というか、信頼が全てです!
よく「教師は授業力がすべて!」と言われます。
確かに、子どもと一番長い時間過ごすのが「授業」です。
また、授業のベースは「学級経営」です。
確かに、いい学級を作ると授業もうまくいくもんです。
でも、やっぱり子どもの気持ちを考えてみてください。
そんな「授業」も「学級経営」も、
先生の働きかけが絶対にベースにあります。
その働きかけをする先生が、
もし「信頼できない先生」なら…
言っていることが正しいと分かっていても
子どもって素直に行動できなくなるもんです。
では、「信頼できない先生」とは具体的にどういう人でしょうか?
それは
「自分たちと関わってくれない」
「自分たちを認めてくれない」
「先生のためにやらされていると感じる」
だと思います。
それぞれの解決方法を1つ1つ見ていきましょう。
心構え①「『やらなければいけないこと』より『やりたいこと』を重視!」
教師…特に担任の先生って、本当に忙しい!
宿題の丸付けから、授業準備。
トラブルが起こると、対応に追われるし
子どもたちには見えない事務的な仕事もてんこ盛り。
多忙極まりない日常であることは間違いありません。
でも、子どもたちにとっては
先生の多忙なんて「そんなの関係ねぇ」です(笑)。
それよりも担任の先生と「話したい」「遊びたい」気持ちでいっぱいです。
良くも悪くも、そんな純粋な気持ちを持っているのが子どもってもんです。
朝のあいさつだけでも…
たった5分の休み時間でも…
給食の時間だけでも…
1日1分だけでも…
「子どもと関わろう」としてみてください。
1分??
1分なんて、絶対だれでも「子どもと関わってるわい」と思うはずです。
でも、そういう形が必要なのではなく
「子どもと関わる時間を持とう」という意識で
実際に子どもと関わることが大事なんです。
授業などの「やらなければいけない」時間での関わりではなく
「子どもとつながりたい」と思う時間での関わりが
子どもには必要なんです。
子どもって、その違いを見抜くピュアさがあるんです。
ほんの少しの時間でも、
担任の先生との時間が過ごせたら
子どもたちは「自分と関わってくれた」と感じます。
でも逆に
子どもたちが「自分と関わってくれない」と感じてしまうと、
子どもは先生と距離を置き始めます。
一度距離を置き始めると、
その距離を縮め直すには、相当な時間が必要です!
とは言っても、
そんなゆとりが作れないんだよ…
という人は、また別記事で一緒に考えていきましょう。
「仕事が速い人は準備に時間をかける。仕事が遅い人は対応に時間をかける。」
という言葉があります。
ぜひ、先手必勝の精神を心がけてみてください。
心構え②「『足りない点』より『できるようになった点』を重視!」
子どもって、自分の長所より短所に目が行きがちです。
大人もそうかもしれません。
その大前提を忘れてはいけません。
そして、もっと大事なことは
短所…つまり「自分の足りない点」は、
人に言われなくても、自分で気づいているもんです。
だから、大好きな担任の先生から
長所…つまり「できるようになった点」を
教えてもらえると、
子どものテンションは一気に爆上がりです。
1か月に1回…
せめて学期に1回…
クラス全員1人1人に
ほんの少しでも
「できるようになった点」を伝えられるようになると
間違いなく、
子どもたちは担任の先生を信頼してくれます!
「自分を認めてもらえている」と安心できます!
もちろん、通知表などの
「やらなければいけない」形ではなく、
直接伝える、保護者に連絡、手紙に書くなどの
「子どものためにやりたい」形で!
「今日は〇〇さんの『できるようになった点』を見つけよう」と決めて過ごすと、
意外とすぐに見つかるもんですよ。
大小の大きさではなく、
「その子のため」という気持ちが重要なんです。
心構え③「『自分の評価や周りの目』より『目の前の子ども』を重視!」
授業や学級経営を、
他のクラスと比較してしまう先生って
意外と多くないですか?
その気持ちは分からなくもないし、
実際に適度に比較することで
子どもたちにも良い刺激になることもあります。
でも、
その「勝負心」や「他人からの目」が
メインになってしまうことで
子どもたちは
「何でそんなことしないといけないの?」
という気持ちになってしまいます。
授業も学級経営も
すべては「目の前の子どもたちのため」にあります。
「他のクラスと比べるため」でも
「学校の評価のため」でもないんです。
ましてや「担任のため」では絶対にないんです!
「△△先生のクラスって、めっちゃきちんとしてるね」と
言われるために
子どもたちに指示を出しては絶対にダメです!
また、先輩の先生や管理職から
「もっと静かに行動させなさい」と言われたから
目の前の子どもたちに
「静かに行動しましょう」と伝えるんではありません。
それはあくまでも
外部からの指摘であり
担任の本心ではないから!
他人の目なんて気にしない!!
もちろん、
そのアドバイスが自分の本心に
ストンと落ちたのなら
自分の言葉で伝えてもいいと思います。
大事なことは
「周りから言われたから」ではなく
自分が「目の前の子どもたちに必要だ」と思うことを
伝え続けることです。
そして、
いつもいつも「子どものため」に動いてくれる先生だと
子どもたちが感じられたのなら、
研究授業や公開授業など
担任の先生にとって重要な場面で
子どもたち自ら
「担任のため」に動いてくれるんです。
その瞬間は、
もう本当にたまらなく
子どもたちへの感謝があふれます。
この快感を一度味わうと
もっともっと「子どもたちのため」に
動きたくなるってもんです。
どんな指示を出すにしても
「目の前の子どもたちのため」という気持ちを
忘れないことが大切ですね。
まとめ
今回ベスト3として、3つ紹介しましたが、
すべてに共通していることは、「子どもたちのため」です。
子どもたちは先生の
1つ1つの言葉かけに
1つ1つの行動に
「自分たちへの愛情があるかどうか」を
自然と察知しています。
温かい言葉はもちろん
時には必要な厳しい言葉にも
「自分たちへの愛情があるかどうか」を
感じるものです。
この3つの心構えを意識して、
子どもたちからの信頼を不動のものとし、
ぜひ修了式の日
「△△先生が担任で本当に良かった!」
「△△先生のおかげで、めっちゃ楽しかったよ!」
と言われてみたいですね。
今後、このブログを通して
具体的にどんな行動や言葉かけ
取り組みや活動があるのか
みんなで考えていけたらと思います。
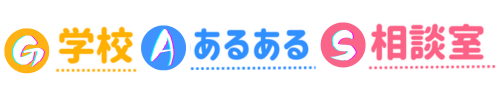
-300x300.png)