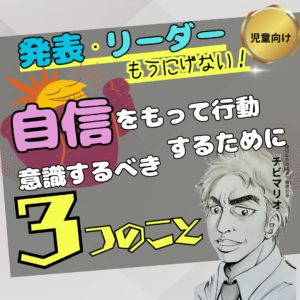【授業の基本】日々の授業づくりで大事にすべき3つの視点

教科書通りに教えているのに
授業がうまくいかないよ

それが実態にそぐわないから
楽しくないんです

でも指導書に書いてある流れは、
全国のお偉いさんが作っているんでしょ?

一番大事なことは、その指導書を
「目の前の子どもたち」に合わせることです
「学校にいる大半の時間が授業」
「学級づくりの基本は授業から」
「教師は授業力が命」
とにかく「授業は大事だ!」というのは
教師として
いつでもどこでも
言われ続けることですね。
楽しい授業ができるようになると
子どもたちが生き生きし始めます。
ただ
「そんな楽しい授業できないよ…」
「全然子どもたちが反応してくれない…」
と悩んでいる先生たちは
多いんじゃないでしょうか??
というより、
ほとんどの先生が
この悩みを持ち続けているはずです。
「授業は永遠の課題」であって当然
あるべきだからです。
そんな授業を少しでも
よりよいものにしていくために必要な
超超基本的な考えを
みなさんで考えていきましょう!
授業を作る上での基本的な考え方
「ガッツリ教え込む授業をしよう!」
「とにかく反復練習をさせよう!」
「少しはゆとりのある時間を作ろう!」
「教科を横断した総合の時間を作ろう!」
「ICTを使おう!」
などなど、
時代に合わせた授業スタイルが
文部科学省から
下ろされてきます。
最近(2025年)では
「個別最適な学びにしていこう!」
「協働的な学びを取り入れよう!」
「子ども主体となる授業にしよう!」が
よく言われていますね。
社会が変われば
授業スタイルも変わる
というのは
当然の流れだと思います。
ただ、
どんな時代でも
これだけは絶対に変わらない
「授業で大事にするべきこと」
があるんです。
それが
「こんな子ども」だから
「こんな教材」を使って
「こんな指導」がしたい
という基本です。
視点①【児童観】~こんな子どもだから~
目の前の子どもたちは
「どんな子どもたち」なのか
これが授業を考える上で
最も重要な視点であり
真っ先に考えるべきことだと
僕は思います。
もちろん
理想的な授業の流れ…
授業で求めたい理想の意見…
イメージすることは大切です。
でも、
目の前の子どもたちの
「今の学力」
「クラスの雰囲気」
「日々の生活感」
などなどを考慮した上で
実際に
目の前の子どもたちが
その理想の授業イメージに
フィットしていますか?
具体的に
目の前の子どもたちが
生き生きとしている姿を
イメージできるのなら
それは
授業計画の段階では
バッチリだと言えるでしょう。
要は
目の前の子どもを度外視した
理想の授業イメージではなく
目の前の子どもたちを想定した
授業イメージであること!
「〇〇さんならできるかな?」
「△△ちゃんなら、ここでつまずきそう」
「□□がまわりを助けられるだろう」
などなど…
具体的な子どもでのイメージ!!
これが重要です。
「教科書の指導書」
「文科からの流行」
「先輩からのアドバイス」
「校内研究テーマ」
「管理職からの圧力」
これらはあくまでも
「参考にすべき材料」
「ベースに取り入れたい考え」であって
最重要視すべきは
「目の前の子ども」
だということを忘れてはいけません。
実態にそぐわない
理想を追い求めただけの
授業だと
子どもはもちろん
先生自体も
全く楽しめません。
高すぎず
低すぎない
課題設定をするためにも
この「児童観」が
とても大事だと僕は思います。
視点②【教材観】~こんな教材を使って~
こんな子どもたちには
教科書の中の
「どの教材(部分)」を使って
授業を作りたいのか
教科書の内容(赤本)を
重要視する先生たちは
ここのポイントを忘れてしまいがちです。
「教科書」や「指導書」は
あくまでも
指導する「材料」であって
「絶対のゴール」ではないんです。
よく言われることですが
「教科書『を』教える」
のではなく
「教科書『で』教える」
ことが大切です!
もちろん
教科書に書かれている内容は
学習指導要領に則って
お偉いさんたちが意見を出し合ったうえで
厳選されている内容なので
めちゃくちゃ
大事なことが詰まっていることは
間違いありません。
ただ、
教材を選ぶうえで
やっぱり
「目の前の子ども」を考えることは
絶対に忘れてはいけません。
その教科書の内容は
目の前の子どもたちを
「ワクワクさせるかな?」
目の前の子どもたちが
「学びたいと思えるかな?」
目の前の子どもたちにとって
「学んでおくべき内容かな?」
「難しすぎないかな?」
という視点で
内容を厳選する必要があります。
教科書にすべてを縛られず
教科書のどこの何を使って
目の前の子どもたちに教えようかな…
そう考えることで
ワクワクしてこないですか?
教科書はあくまでも 教えるための材料です!!
視点③【指導観】~こんな指導がしたい~
こんな子どもたちだから
こんな教材を使って
「どのように指導」していきたいのか
「どんな力」をつけさせたいのか
ここが最後に
児童観と教材観を考慮した上で
オリジナリティを爆発させるところです。
指導書はあくまでも
具体的な児童は度外視した
理想の授業イメージで
構成されています。
「これができたら完ぺき!」
という課題設定や目標設定と
なっていて
理想論満載です(笑)
ただ、
だからと言って
まったく参考にしないのではなく
「目の前の子ども」の実態に
合わせる形で
取り入れることが
有効的な活用方法だと
僕は思います。
例えば
指導書には
1時間の授業の中で
3つの活動が設定されていたとします。
でも、
目の前の子どもを
イメージした場合、
「絶対に時間内に終わらない」
「この活動は難しすぎる」
と感じたのなら
その1つの活動を
充実させる形に変えて
取り組むのもありなんです。
もしくは、
その3つの活動を
それぞれ1時間ずつに分けて
3時間構成に
作り変えてもいいんです!
要は
単元全体を通して
「どのような力」をつけたいのかを
ハッキリさせた上で
それを段階的に達成できるよう
目の前の子どもに合った活動を
計画すればいいんです。
指導書通りなんて
子どもたちからすれば
「おもんない授業」
に決まっています!
声には出さずとも
「おれらに合ってない!!」
っていうオーラを
ガンガンに出してきます。
一人でもくもくと取り組ませる活動
人とガンガンに関わらせる活動
全体で意見を交流させる活動
個別で見たら
もっともっと適切な活動はあるにしても
クラス全体で考えても
雰囲気にフィットする活動って
絶対にちがいます!
やっぱりこの「指導観」でも
「目の前の子ども」を
重要視することが
欠かせないポイントと なってきますね。
まとめ
今回ここで紹介した
「こんな子ども」だから
「こんな教材」を使って
「こんな指導」がしたい
という考え方は
授業づくりの超基本!
とは言うものの
毎日考えないといけない授業で
毎回毎回ここまでていねいに
考えることは不可能です。
ただ、
すべてに共通する
そして
永遠に変わることのない
「目の前の子どもを最重要に考える」
というポイントだけは
常に持ち続けて
授業を作っていきたいですね。
まわりからの目を気にして
「やらなければいけないこと」
に追われる教師より
目の前の子どものために
「やりたいこと」
「やらせたいこと」
を優先できる教師って
すてきだと思いませんか?
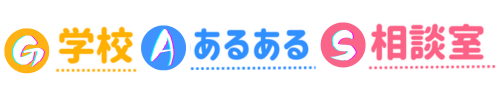
-300x300.png)