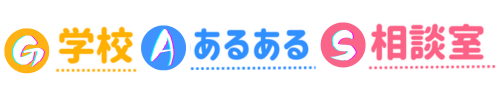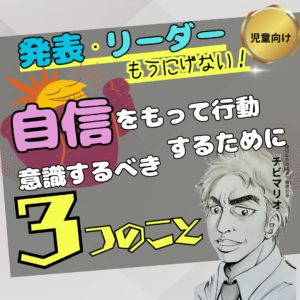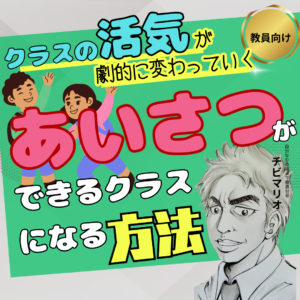【保護者必見】子どもを安心して預けられる学校にするための「保護者ができる3つのと」

「うわぁ!!うちの子の今年の担任、
うわさの〇〇先生や…

それは俗に言われる、
担任ガチャの『ハズレ』ってことですか?

だって〇〇先生のクラスって、
いつも落ち着きがないって聞くし…

そのすべてが担任の責任ではありません。学校として問題があるのかも…。
そして保護者として、できることもあるんです。
子どもにとっての
1年間はめちゃくちゃ大きい!
その1年間で
「どんな人」に出会い
「どんな経験」をするのかによって
成長が大きく変わります!
それは紛れもない
事実です!!
だから
その一点においても
子どもにとって
「担任の先生」が誰になるのかは
爆発的な影響力があることは
間違いありません。
ただ、
そんな「重要な1年間」を
担任の先生に
すべて任せるんではなく
保護者として
「できること」もあるんです。
担任の先生に対して…
学校(管理職)に対して…
自分の子どもに対して…
どんなことができるのか いっしょに考えてみまし①ょう!
①担任に対して
保護者のみなさんから見て
「担任の先生」っていう仕事は
ラクそうに見えますか?
大変そうに見えますか?
正直、
「担任の先生」って
激務極まりないんです!!
その感じが
全身からあふれ出している先生も
全く感じさせない先生も
いろんな先生がいますが
誰しもに共通して
「担任の先生」という仕事は
激務なんです!
まず、そこだけは
ご理解ください
ただ、
担任として
いろんな仕事がある中、
やっぱり一番大事にしてほしい内容は
「いいクラスを作る」
「子ども1人1人を大事にする」
だと思います。
そこに一番
時間や思いをかけられるよう
サポートしていくことが
保護者のみなさんが
「担任の先生に対してできること」
です。
具体的には大きく2つ!!
1つ目は、やはり
「先生の味方になる」ことです!
「先生の味方ですよ!」
「先生のサポートしますよ!」
っていうオーラを出す……
だけでなく、
実際に
直接会って伝えたり
電話で話したり
連絡帳や手紙に書いたり
してみてください!
そのちょっとした
温かさが
担任の先生にとって
ものすごく大きな支えになって
1年間がんばるパワーに
つながります!
これ、ものすごく大事!!
そうした上で
2つ目!
それが
「学級経営方針を明確にしてもらう」
です。
学級経営方針とは
簡単に言うと
どんなクラスにしたいのか
どんな子どもたちを育てたいのか
そのために
どういうことは認め
どういうことは厳しくする
などの
教師の想いの軸です。
本来なら
担任の先生自身が
自ら
子どもたちに伝えたり
通信などで保護者に発信したり
もしくは
公表はしていなくても
自分の心の中で
確固たる強い方針が
存在しているんです!
ここがしっかりしている
担任の先生は強い!
うまくいかない時期があったとしても
必ず修了式には
いい形で終われます!
それくらい
この「学級経営方針」って
大事なんです!
保護者のみなさんが
「ハズレだぁ~」と
思ってしまうような先生って
実は
「学級経営方針」を決めていなかったり
まわりの状況によって
この軸をブレブレに揺らしたり
してしまうんです。
だから
クラス作りがうまくいかなかったり
子どもから不満が出てきたりして
保護者のみなさんから
不安に思われてしまいがちなんです。
担任の先生に
この軸をきちんと持ってもらうためにも
「学級経営方針」を聞かせてもらう
っていうのは
大事なことなんです。
※「学級経営方針」というのは私が勝手に作った名前なので、
「1年間のヴィジョン」「1年間の計画」を教えてくださいって言ってみてください。
②学校に対して
もう一度言います。
担任の先生は
激務です!
それでも「やりたい」と
思っている時点で
僕は尊敬に値すると思っています。
ただ
世の中には
「なんであんな人が先生やってんの?」
って思うこともあると思います。
ぶっちゃけ
「素質」の問題…
つまり
採用した教育委員会に
責任があることもあります。
今回はそれとは別に
学校という「組織の雰囲気」に
問題がある場合が
かなり高い割合で存在するんです。
こっちの問題で
保護者として
学校に対して「できること」が
あると僕は思っています。
それは
校長や教頭などの管理職や
学校全体を支える立場の先生に
「1つのクラスにいろんな先生が関わるような学校にしてほしい」
という想いを伝えることです。
担任の先生だけに
任せっきりのクラスって
やっぱり良くないんです。
めちゃくちゃすばらしい先生が
担任のクラスであったとしても
やっぱりいろんな人が
1つのクラスに関わる方が
子どもたちの伸びしろも
全然変わってきます!
じゃあなんで
そもそも
そうやって
1つのクラスにいろんな先生が
関わるようにできていないのか…
その原因は
(1)そういう体制にしていない
(2)職員間の連携が悪い
(3)管理職など特定の人物の圧が強い
などです。
(1)
担任は担任
支援は支援
専科は専科
確かにメインの役割は
立場によって変わります。
でも、大前提として
学校全体を…
1つのクラスを…
1人1人を…
大きなチームで育てていく
という意識が大切なのですが
そもそも
そういうような体制を
作っていない学校も
まだまだ存在するように思います。
(2)
これはシンプルに
どんな社会にでも存在しますが
職員間の雰囲気が良くないならば
1つのクラスを
多くの目で育てることなんて
不可能だと思います。
(3)
かなりのトップダウン体制
担任の個性を認めない
そういう雰囲気だと
担任の先生の一言一言は
自分の本心ではなく
「言わされている」言葉になってしまい
子どもたちに伝わりません
そうなると
子どもの心に届かないどころか
前述の
「学級経営方針」を決めていたとしても
軸がブレブレになってしまうんです。
これらのような原因で
学校がチームとして
動いていないなと思ったら、
即、学校に
電話で相談してはいかかでしょうか?
ただ、
気をつけていただきたいのは
こういう内容に関しては
担任の先生に言ってはいけません!
それは逆効果となってしまいます。
学校全体の体制に関しては
「担任の先生」ではなく
全体に関わる先生に
連絡することを忘れないでください
③わが子に対して
ここは意外と盲点ですが
結構重要なポイントです。
子どものタイプに分けてお話しします
(1)学校での楽しかった話をよくする子
ここに関しては安心ゾーンです。
いっしょに喜んであげたり
楽しかった内容を掘り下げたりして
子どもの気持ちに寄り添うことが
最も楽しいし
最も効果的だと思います
(2)学校での嫌だった話をよくする子
ここはデリケートゾーンです。
「嫌だった話をくわしく聞く」
それは絶対にしてあげてください
家族に自分の味方がいる
嫌な気持ちを受け入れてくれる
これは子どもにとって
必須の状況です
気持ちをくわしく聞き取った際に
「それは嫌だったね」
「しんどかったね」と
同調することも
子どもにとって
大きな安心へと変わります
ただ
ここで保護者として
気をつけなければいけないことは
「子どもの話が絶対正しいわけではない」
という受け止め方です
そして絶対にダメなのが
子どもといっしょになって
友だちのことや
担任の先生のことを
悪く言うということです
子どもはどうしても
自分の被害者意識をメインで話します
もちろん
それがウソだという気持ちで
聞く必要はありません
でも、
自分自身もよくないことをしていたり
おおげさに伝えたりしてしまうことも
子どもの中では
日常茶飯事です!
子どもの話を
すべて鵜呑みにしてしまうと
誤った対応や学校への連絡になってしまい
今後の学校との関係に
今後の担任との関係に
壁ができてしまうかもしれないからです。
そして
最悪の状況は
子どもが
担任の先生を
まったく信じられなくなることです
子どもの前では
全力で受け止めながらも
自分自身では
話半分で聞き、
定期的に様子を見たり
内容によっては
担任に相談したりする必要があります。
担任に連絡する際も
「うちの子が絶対ではないと思うんですけど…」
というスタンスで
子どもから聞いた話を伝えて
学校で事実の確認を
お願いすることで
担任としても
前向きな対応がしやすくなります
子どもを100%信じた保護者が
我が子を全力で守るスタンスで
連絡された場合、
正直担任は
冷静な対応ができなくなり
今後の対応にもミスが生じます
子どものためにも
「協力をお願いする」というスタンスを
忘れないでください
(3)学校の話をほとんどしない子
ここは、勘違い多発ゾーンです
子どもからの情報がない
学校からの情報もない
そういうときの
親の気持ちって
2パターンですね!
全く気にせず
子どもを送り出せるパターン1
ここは
無関心すぎなければ
安心です
勝手に想像したり
うわさ話に翻弄されたりして
不安になってしまうパターン2
後者の方の解決方法は
ずばり
保護者から子どもに
「最近どう?」
と聞き出すことが
最も効果的だと思います。
それでも
「何もない!」
「だいじょうぶ!」
というのなら
信じてあげるのもよし!
それでも心配なら
学校に連絡し
学校での子どもの様子を
担任の先生などから
正確に聞き出す必要がありますね
保護者間での
うわさ話を信じすぎて
我が子に
間違った情報を伝えたり
偏った判断を植え付けたりしないよう
気をつけてほしいなと思います
まとめ
年度初めの担任発表
子どもといっしょに…
いや、子ども以上に
ドキドキする気持ちは
めちゃくちゃ分かります。
ただ、
すべてをガチャに任せず
保護者として
自分自身にできることを
実践してみてください。
①担任に対して
「明確な学級経営方針を公表してもらう」
②学校に対して
「たくさんの先生からの見守りを要求する」
③子どもに対して
「子どもの気持ちに寄り添いつつも、客観的な心で冷静に対応する」
そうすることで
「子どもの1年間」が
充実したものに変われば
実は…
「保護者にとっての1年間」も
充実したものに変わります。
子どもの貴重な1年間を
「いっしょに楽しもう」
というくらいの保護者からの気持ちって
意外と重要なんです!
ぜひ
以上の3つの方向からの行動で
「ハズレ」と思っていたガチャを
自分自身の力で
「アタリ」に変えてみてください(笑)
超気持ちいいですよ!