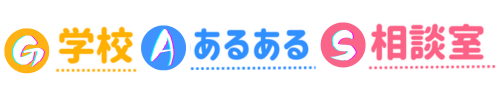【クラス作りの超基本】あいさつが変われば、クラスが変わる!

クラス全体的に活気が
あまり感じられないんだよね…

クラスにいる子どもたちの性格もあるから
活気があることが正解というわけではないけどね

それは分かっているけど
もう少し明るいクラスにしたいな…

それなら、どんな子どもたちにも必要な
『あいさつ』から変えていってはどうですか?
クラスに明るさが足りない…
もっと自由に発表し合えるクラスにしたい…
男女問わず、いろんな人とつながってほしい…
そういう理想像が膨らむばかりで
具体的にどうすればいいのか迷うことってありませんか?
1つ1つを深めていくには
いろんな対策は必要だと思いますが
どの理想像にも共通して重要なことがあるんです
それが…
「あいさつ」です!!
あいさつが変われば、クラスが変わる!
これは紛れもない事実です。
なぜ、あいさつが重要なのか
どうすれば、すすんであいさつをする子になるのか
一緒に考えてみましょう!
あいさつができる子どもたちになると
ふだんの授業もいっそう活気が増してきますよ!
①なぜ、あいさつが重要なのか
「あいさつはコミュニケーションの第一歩!」
この言葉を聞いたことのある方は
多いのではないでしょうか?
まさにこれが
「あいさつが重要」という理由です。
「おはよう」という
一言だけでも交わせる毎日が続くことで
仲の良い友だち同士はもちろん
あまりふだんは関わらないような子同士でも
つながるようになるんです。
何気ない会話を
日ごろからできる子同士なら
もし「おはよう」がなくても
心がつながった日々を過ごせるかもしれません
でも
自分からは話しかけにくい子…
偏った友だちとばかり話す子…
同性だけとしかつながらない子…
クラスにいませんか?
そんな子たちにとって
「おはよう」というあいさつは
心をつなぐ魔法の言葉となるんです!
「おはよう」という一言だけでも
いろんな子と交わせるようになるだけで
すべての子どもたちの心が
一瞬つながるんです!
あいさつができれば「クラスがつながった」
とは言えませんが…
まちがいなく
「1つにつながったクラス」は
あいさつが気軽にできるんです。
「おはよう」
「おはようございます」
じゃなくても
「よっ!」
「うっす!」でも
全然かまいません!
とにかく
あいさつから1日が始まるよう
声かけをしてみませんか?
②あいさつができるクラスにするために
いやいや、
とは言うものの
そんなに簡単にあいさつをする子どもたちなんて
なりやしないですよ!
という声が聞こえてきますね。
それは百も承知です。
でも、あいさつができるようにするための
重要なポイントというものが存在します
そのポイントとなる場面を見逃さず
1つ1つ抑えて
クラスに返していくことで
クラス全体の雰囲気が少しずつ変わっていきます
順を追ってみてみましょう!
(1)「あいさつができるクラスにしよう」と呼びかける
これは超基本です
まずはリーダーとして
担任の先生から子どもたちに
「あいさつができるクラスにしていこう!」
と呼びかけることで
クラスのみんなで
「あいさつが大事」という心構えを
持たせるようにしましょう!
みんなが1つの目標に向かって
気持ちを一つにするって
めちゃくちゃ大事です!
(2)「あいさつを返す人が一番!」と教える
そうやって呼びかけた次の日、
必ずやってほしいこと…
それが
「誰よりも早くに教室で待つ」
です!
教室に子どもたちが入ってくるたびに
担任の先生として
相手よりも先に
「おはよう!!」と元気よく
声をかけてください!
これ…
「相手よりも先に」がポイントなんです
理由は、(3)でお伝えします。
で、
そんな先生の「おはよう!」に
必ず1人は
「おはようございます!」と
返してくれる子が現れます!
その子の名前を何かにメモし
朝の会で
「〇〇さんが今日、先生の『おはよう』に元気よく返してくれました」
という話から
「あいさつは一人ではできない」
「あいさつを返してくれる子がいると超ハッピー」
「あいさつを返してくれる子がいるとクラスは変わる」
ということを伝えてください!
次の日から
「おはよう」と返してくれる人が
1人でも増えるはずです!
ちなみに初日から
あいさつを返してくれる子が大勢いた場合は
「今日、〇人の子が、先生の『おはよう』に元気よく返してくれました」
という話でもいいと思います。
「俺も入ってるかな?」
というドキドキがまた
子どもたちの好奇心を刺激しますから!
PS:どうしても家庭の事情などで
朝一から教室にいることが不可能な場合は
・代わりに違う先生に入ってもらう
・クラスのリーダー的存在の子に上記の役割を託す
・朝一じゃなくても担任が教室に入るときに「おはよう」と元気よく言い、
そのときに「おはよう」を返してくれた子をピックアップする
などの対応は必要ですね。
3つ目は絶対にできるはず!
(3)教室に入るときに「おはよう」が言える子を見つける
「あいさつを返す子」が増えてきたなら
次はあえて
教室で待っている先生は
「おはよう」を言わないでおきましょう!
そうすると
必ず先生よりも先に
「おはよう」と言ってくれる子が現れます!
そのあとの流れは(2)と同じで
朝の会で、全体に伝えてあげてください!
「自分から進んであいさつできる子ってステキ!」
と、子どもたちの頑張りをシェアするだけで
もっともっと子どもたちは
あいさつをしようという気持ちになってきます!
(4)あいさつリーダーを子どもから募る
そんな順序でいくと
子どもたち同士で
「よっ!」
「おはよっ!」
とか交流する場面が
必ず現れます
そうなったらいつもの流れ!
朝の会で全体に共有しましょう!
「先生があいさつしなくても、子どもたち同士であいさつしている場面を見かけました!
先生はめちゃくちゃ嬉しかったです!」と!
そんな流れから
もっともっとあいさつができるクラスにしたい!
そのためには
先生の代わりにあいさつを広げてくれる子どもが必要!
と投げかけてください!
「あいさつリーダー」という役割を
担ってくれる子を決めて
あとは、先生は裏方に回ります!
あいさつができている場面を子どもたちで共有したり
もっとできるようにするための話し合いをしたり…
そのサポートを
先生がするんです!
あいさつを子どもたちだけに
ゆだねる時期になりましたね!
(5)成長を実感できるようにする
そしてここが最後の重要ポイント!
今の流れで1か月…
いや2週間は、
高いあいさつ意識を持続できます
ただ
これだけだと
間違いなく
子どもたちの意識は下がっていき
「一時的にあいさつを頑張ったクラス」
になってしまいます
これを一時的なものにしないために
「あいさつができていることを実感させる」
ことが重要です!
例えば
毎日の帰りの会のとき
「今日、5人以上と『おはよう』が交流できた人?」
と投げかけて
半数以上の子が手を挙げたなら
教室のどこかにシールを貼るなど
小さなことでもいいので
あいさつを振り返る場面が必要です。
で、このシールが一定数貯まったら
「みんな遊びの時間を作る」や
「宿題なしの日を作る」
などのご褒美があってもいいかもしれません。
その「シール作戦」や「ご褒美の内容」を
先ほどの(4)のあいさつリーダーと
いっしょに考えて
あいさつリーダーから
みんなに提案させることで
より一層、子どもたちは
成長を実感できますね!
で、
公表はせずとも
先生の中で
「全員が手を挙げた初日」には
シール関係なく
「宿題なし」などのご褒美を
作ってあげるのも
子どもたちのモチベーションにつながりますね!
③あいさつができるクラスのメリット
そうして
あいさつができるクラスになっていくにつれ
あいさつ以外の場面で
成長を実感できるようになります
その代表例は以下の3つ!
(1)友だち同士がつながる
いろんな子に「あいさつをしよう」という仕掛けから
ふだんあまり話さない子と関わる子が増えたり
高学年あるあるの男女の壁も消えていったりします!
そういう
先生が目指したい姿を
目撃したときに
全体にシェアするという
いつもの流れは忘れずにいきたいですね。
(2)授業中に発表する子が増える
これ意外と実感できます。
「おはよう」が言えるようになると
「1+1=」のような
簡単な問題や
「『平』の読み方は?」のような
ドリルを見れば答えが分かるような質問など
答えがハッキリとしている投げかけに
手を挙げる子が増えるんです!
あいさつを返してくれる仲間たちの前なら
「ちょっとくらい発表してみようかな…」
と思える子どもの心理というやつです
(3)自分たちならできるという自信が生まれる
あいさつは成長を実感しやすい行動です
そんなあいさつが
「できるようになった」という実感が
「俺らならできる!」
「今年のクラスは一味ちがう!」
という自信につながり
いろんな行事での取り組み方が
変わってくるんです
もちろん上記の3つ以外にも
いろんな場面で
「あいさつの効果」が表れるはずです
④あいさつができるクラスにするときの注意点
そんなメリットいっぱいの
「あいさつ」ですが
気をつけないといけないことがあります!
それは
「無理やりさせない」
です。
先ほど紹介した流れで
ほとんどの子は
あいさつをしようと頑張ってくれます!
その子をホメることは
ドンドン続けてもいいのですが
そんな空気の中、
絶対に「(すぐには)あいさつをしない子」も
存在するんです。
これ
「(すぐには)」というのも
ポイントです!
で、
「なんであいさつしないの?」
「あいさつしなさい!」
などの追及や指導は
絶対にタブーです!
あいさつをすることは良いことですが
あいさつをしないことが悪いことではないからです!
これ
めっちゃ重要!
「あいさつをする=良い」
「あいさつをしない≠悪い」
ではないんです!
あいさつをしない子は
しない理由があるんです!
そこを理解する担任
そして
クラスの子どもたちでなければ
逆に
「あいさつ」が理由で
クラスの居心地が悪いと
感じてしまう子も出てきます
する子はホメるが
しない子を叱らない
そして
クラスの雰囲気に
「しない=悪」というオーラを
生み出さないように してください!
⑤まとめ
「あいさつをしよう」という投げかけだけでは
子どもというのは
変わっていかないものです
具体的なしかけがあればあるほど
子どもたちは
自分たちから動いていくもんです!
学級開きでは、
ぜひ
「あいさつができるクラスにしよう!」と
呼びかけてみてください!
そして
自分たちの変化を
子どもたち自身に
実感させてあげてください!
それだけで
子どもたちの中では
「なんか今年のクラスは違うぞ!」
「なんか楽しみになってきた!」
という気持ちが
芽生えると思います!
あいさつが変われば
子どもたちが変わります!
一度
この重要性を実感すると
他の先生にも
教えたくなるくらい
効果抜群なのが
この「あいさつ」です!
ぜひ試してみてください!